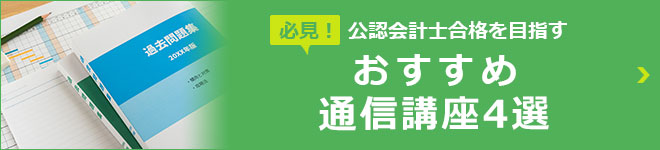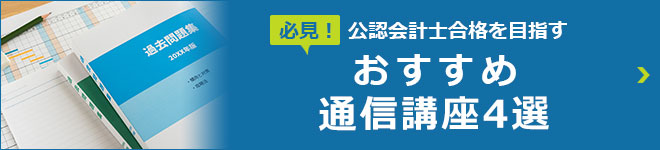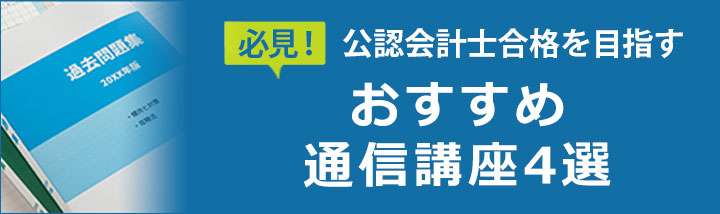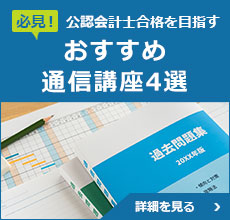公認会計士と学歴の関係性
公開日: |更新日:
公認会計士を目指している人にとって、学歴も気になる部分なのではないでしょうか。実際に公認会計士として働いている人の学歴を見ると、高学歴が多いのでそのような気持ちになるのも分かります。ここでは実際に学歴との相関性があるのか、公認会計士との関係性をまとめてみました。
公認会計士は高学歴が多い
公認会計士は決して学歴で差別されるような資格ではありません。しかし、公認会計士試験に合格し、活躍している公認会計士の学歴を見ると、近年に関しては慶應義塾大学や早稲田、明治といった大学に加え、東京大学や京都大学など国立大学卒者の姿もあります。これらの事実を鑑みると、公認会計士は学歴の高い人間が多いとされていると感じるでしょう。
ただし、決して偏差値の高い難関大学を卒業した方が試験が有利になるといったことはありません。
公認会計士試験の合格者に高学歴が多い理由
決して学歴によるアドバンテージがある訳ではありませんが、難関資格とあって頭脳明晰かつそれなりに学力が求められる点は間違いありません。公認会計士試験は出題範囲が広いので、勉強に関してもある程度コツをつかむ必要になります。難関大学を卒業しているということは、既に一度、大学入試という「難関」を突破した実績があることです。大学入試時の経験を元に、公認会計士試験の勉強を組み立てて合格した公認会計士もいるでしょう。
テストの点数はもちろん、どのように勉強するのかなど、勉強の質も問われます。公認会計士に高学歴が多いのは、勉強の質が問われる入試を一度クリアしている実績があるからこそと考えられるでしょう。公認会計士試験では暗記力や論理的思考と、様々な能力を求められます。難関大学を突破した方は、成功した経験をもとに細かな計画を立てているとも考えらえるでしょう。
合格に高学歴かどうかは関係ない
公認会計士試験の合格者、つまりは既に活躍している公認会計士に高学歴が多いのは一つの事実です。ただ、決して学歴によって試験における優遇措置がある訳ではありません。公認会計士の試験は受験資格の条件がなく、この点は国家資格としては異例です。司法試験であれば法科大学院の修了者であり、かつ司法試験予備試験の合格者でなければ受けられません。税理士試験であれば大学3年次以上で一定の単位を履修したり、簿記試験1級に合格している人間であったりしなければならないなど、様々な条件が設定されています。
しかし、公認会計士に関しては受験資格がないので、最終学歴が大卒ではなく高卒、あるいは中卒であっても問題はありません。
実は2005年以前、公認会計士も大学卒業あるいは1次試験合格など、他の国家資格同様受験の条件が設定されていました。2006年度以降に関しては受験資格の制限がなくなったので、学歴だけではなく年齢や性別、さらには国籍さえも問われていません。もちろん合格するためには試験にて良い点数を取ることが求められます。それでも学歴に関係なく、自分自身の努力にて合格をつかみ取ることができる点は、公認会計士試験のメリットでしょう。
公認会計士は専門学校でも目指せるのか
公認会計士は誰もが受験資格を持つものです。しかし、あくまでも「受験資格」であって、合格するためにはもちろん勉強しなければいけません。特に専門学校は様々な試験に特化しているので、合格への最短コースを生徒に導いてくれるでしょう。特に実績の豊富な専門学校であれば説得力もあります。
もちろん独学でも勉強は可能です。ただ、公認会計士試験の難しさの一つである出題範囲の広さをが壁となります。独学となると、膨大な範囲全てを一人でカバーしなければなりません。実績の豊富な専門学校であれば、勉強方法からサポートしてくれるので課題も見えやすいのがメリットです。また、他の生徒の存在が刺激になります。もちろん、学費がかかることも含め考慮しなければならない点はありますが、専門学校は公認会計士試験合格のための選択肢として、検討しておいて損はないでしょう。