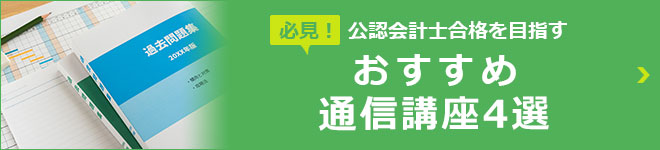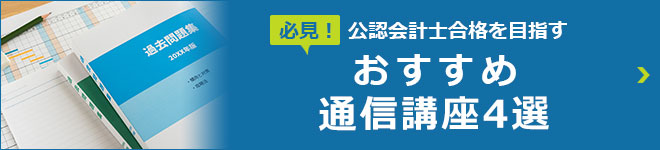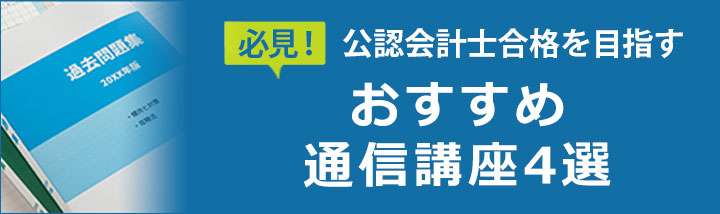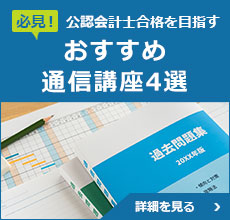公認会計士登録に求められる「実務経験」とは
公開日: |更新日:
公認会計士になるためには、公認会計士の試験に合格するだけでは不十分です。公認会計士と登録するためには業務補助や実務従事と言った実務経験や実務研修及び修了考査が必要となります。このページでは公認会計士の登録で求められる実務経験について、分かりやすく解説していくのでチェックしてください。
公認会計士登録に実務経験が求められる理由
非常に難易度の高い公認会計士の試験をクリアしたにも関わらず、なぜ実務経験が求められるのでしょうか?それは公認会計士として必要な知識をどんなに詰め込んだとしても、それは教科書に書いてある知識を知っているだけです。実際には応用力が必要となり。実務でしっかりと経験を重ねているからこそ問題を解決できる事例も数多くあります。
また一人で公認会計士として業務を担うためには、ある程度実務経験を積む必要があるでしょう。たとえば問題が発生するたびに先輩の公認会計士に質問ばかりしていれば、クライアントから信頼されません。そう言った意味でも公認会計士としての実力を高める必要があるため、実務経験が大切なのです。
公認会計士登録に必要な実務経験の種類
- 業務補助
- 実務従事
公認会計士になるために欠かせない実務経験には、上記の二つがあります。この業務補助・実務従事の二つを経験していると、両方の期間を通算可能です。それぞれについて具体的に見ていきましょう。
業務補助とは
業務補助は監査法人・企業などに就業し、仕事を行いながら公認会計士としての必要となる知識・技術を習得していきます。この際、雇用形態は関係ないため常勤・非常勤どちらで経験を積んでも構いません。ただ1年間で2つ以上の法人監査の照明業務を実施する必要があります。
また監査法人に就職し監査を行うだけでなく、銀行業務や大手の会社にある経理部などの財務分析業務を行うことも業務補助に含まれます。しかし簡単な記帳業務は適応外なので要注意です。企業自体に業種の指定はないため、決算業務。工場経理業務・予算実績管理業務などの業務が該当するでしょう。金融機関なら貸し付け・債務の保証などの資金運用に関わる業務が関係しています。公務員なら会計検査・税務検査が該当し、国税局の税務調査業務や市町村における財務監査などが該当。
実務従事とは
一方、実務従事とは財務に関係する監査・分析などの実務に従事することです。国によって、どんな業務が当てはまるかが定められています。
国や地方公共団体であれば、会計検査やそのほかの法人における原価計算の財務分析事務が該当するでしょう。また監査・国税に関する調査・検査の事務・金融機関や保険会社なら貸し付けなどの資産運用事務も含まれます。つまり定められている項目が細かいため、必ず確認しておきましょう。
実務経験を証明する方法
公認会計士試験を合格した者によって、各勤務先が異なるので実際の証明が必要になってきます。まず証明書には「業務補助等の報告書受理番号通知書」が交付されているため、要件をクリアしていることが証明されているのです。
さらに、この通知書が交付されたのちに業務補助等報告書や添付書類を金融庁の長官宛てに提出します。報告書には書式が定められているので注意しましょう。この報告書を発行できるのは業務補助などを行った公認会計士・監査法人、法人の代表です。法人の概要を記載した書類や、実務を行った人が作った資料などが必要になることもあります。
「2年の実務経験」は週何日働けばいい?
公認会計士になるためには、実務経験を2年以上行うことが求められています。ただ2年以上というのは業務補助と実務従事によって、考え方が異なるので注意しましょう。業務補助は監査法人の代表さえ認めていれば1週間当たりの日数は決まっていません。一方の実務従事は常勤で2年間と定められているので、非常勤であれば2年間で要件がクリアできないケースもあります。たとえば非常勤として常勤者の3分の1程度の勤務なら、実務従事の期間も常勤の人の1/3となるため、同じような環境下で要件をクリアするために、常勤者の3倍の時間がかかるでしょう。
この期間は公認会計士の試験に不合格であっても、公認会計士試験をクリアする前の期間も含みます。ただ公認会計士の試験自体非常に難易度が高いので、合格してから実務経験を積むケースがほとんどです。
実務経験はどこで行う?
監査法人
実務経験を行う場所として一般的なのが監査法人です。公認会計士試験合格者のほとんどは、監査法人にて業務補助の経験を積みます。監査法人は公認会計士として必要なスキルを身に着けるのに適した環境であり、ここでしか味わえない経験もあるかもしれません。
また、雇用形態は常勤だけでなく非常勤であっても実務経験として認められるため、この点をありがたいと感じる人もいるでしょう。なお、監査法人にて2年以上従事すれば、問題なく実務経験の条件をクリアできます。資格登録の条件には「2年以上の実務経験」とありますが、業務補助だけでも大丈夫です。
大手監査法人で実務経験を行うメリット
公認会計士になるための実務経験のクリアを目的としている場合は、どこの監査法人に従事しても問題ありません。しかし、「公認会計士としてさまざまな経験を積みたい」と考えている人は、大手監査法人で実務経験を行うのが良いでしょう。
なぜなら、大手監査法人のクライアントは大手企業であることが多いからです。また、大手監査法人は海外の会計事務所と連携を図っているケースも多いので、将来的にグローバルな活動を志す人にも向いています。
中小監査法人で実務経験を行うメリット
中小の監査法人は、大手監査法人のように大手企業がクライアントであることは少なめですが、大手監査法人では味わえないような貴重な経験ができます。具体的に、中小の監査法人では、監査のみならずコンサルティングやM&Aなどの業務に携わることが可能です。
2年間の実務経験と並行して、監査以外の業務も経験してみたいという人にとっては、非常に有意義な職場となること間違いありません。また、早いうちからマネジメント業務にも関わりたい人も、中小の監査法人が適しているといえます。
会計事務所
会計事務所の数は非常に多く、小規模な会計事務所から大規模な会計事務所までさまざまです。しかし、どの会計事務所であっても実務経験として認められるわけではありません。公認会計士になるための実務経験の条件には、会計事務所のサービスが会計監査であるか、資本金5億円以上のクライアントに対する財務分析事務のどちらかを満たす必要があるのです。
大手会計事務所の場合は、どちらの条件も満たしているケースがほとんどでしょう。また、資本金5億円未満の小規模な会計事務所でも、資本金5億円を超えるクライアントを相手とする場合は実務従事に含まれるので問題ありません。どちらも実施していない場合は実務経験として認められないので、事前調査は必須です。
銀行・保険会社
銀行や保険会社といった金融機関の業務では、資金の運用を行う貸付や債務保証などが実務として認められています。それ以外の業務を担当する部署が実務経験に含まれないので、あらかじめ確認しておきましょう。
なお、具体的な実務従事とは、銀行での法人融資の業務や保険会社での資産運用を目的とした財務内容調査、投融資審査などが挙げられます。
そのほか条件を満たす企業など
監査法人や会計事務所のほかに、事業会社の経理職や公務員は公認会計士になるための実務経験に含まれます。事業会社の経理職として実務経験を積む場合、所属する企業の資本金が5億円以上である、または資本金額5億円以上の法人を対象に業務を行うことが条件です。業務においては、財務報告に係る内部監査や財務書類の分析などを行います。
また、公務員として国や地方公共団体の期間に従事する場合は、税務調査を担当することで実務従事と認められるでしょう。
公認会計士登録に必要な実務経験に関するまとめ
公認会計士として登録するためには実務経験を必ず積む必要があります。しっかりと実務経験を行うことによって、公認会計士としてのスキルも高まるでしょう。この実務経験の期間中に数多くの経験をおこなうことで、将来的にもプラスとなります。「せっかく試験に合格したのに…」とマイナスで考えるのではなく、クライアントから信頼される公認会計士となるための試練と考えるようにしましょう。