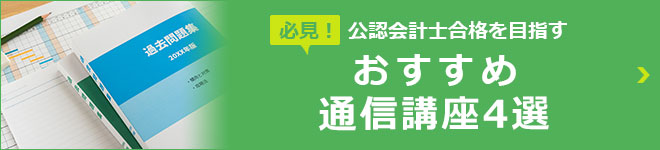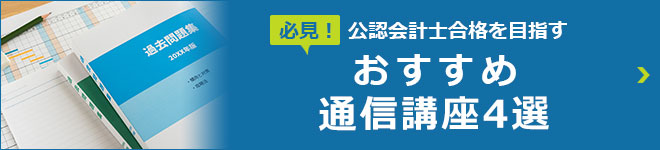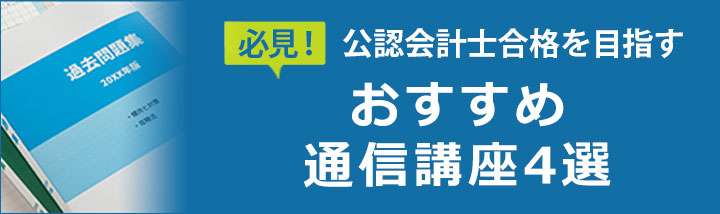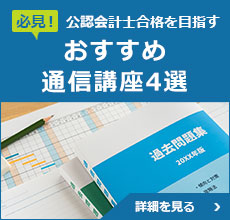公認会計士試験の勉強の順番って?
公開日: |更新日:
公認会計士試験を受けるには、数多くの科目を勉強しなければなりません。しかし、どこから手を付けていいか見当もつかない人もいるでしょう。
ここでは「一体何から勉強したら良いの?」とお悩みの方に向けて、公認会計士試験の勉強の順番や優先順位のつけ方について紹介しています。
公認会計士試験の勉強の順番
受験科目は全部で9科目。そのうち必須科目は5つとなっています。残りの4科目は選択となり、論文式試験の際に1科目だけ選んで受けることになります。実質は必須科目5科目と選択科目1科目の計6科目となるため、どの科目を選択するかを決めておけば、効率良く学習ができるでしょう。
選択科目は必須科目の内容をよく理解した上での学習が好ましいため、必須科目は以下の順番で勉強していくのが良いです。
- ①財務会計論
財務会計論は計算部分の「簿記」と理論部分の「財務諸表論」に分けられます。同じ論点を同時に勉強するのが効率的です。 - ②管理計算論
こちらも財務会計論と同様に、計算と倫理から成り立ちます。短答式試験においては別の科目としてカウントされますが、論文式試験では2つを合わせて「会計論」として扱っています。 - ③企業法
企業法は膨大な量の知識を詰め込まなければならないため、なるべく早くから勉強を始めるのが好ましいです。 - ④租税法
計算と理論の配点比率は6:4程度です。計算のボリュームが膨大なので、計算を学んでいるうちに理論で必要となる知識が勝手に身に付きます。 - ⑤監査論
他の科目に比べて分量が少なく、勉強の開始時期が少し遅れても問題ありません。ただ、監査論のせいで不合格となった受験生も多いので、後回しにし過ぎないよう注意しましょう。
優先順位のつけ方
公認会計士の勉強内容の優先順位は、学習時期ごとの重要性について考慮しなければなりません。間違った努力だった場合には成果が出づらくなってしまうので、重要性の判断は大切にしましょう。
学習時期ごとの重要性は、1人ひとり異なります。そのため、「学習時期の計算が分からない」という人は、通信講座で聞いてみるといいです。これまでに多くの合格者を輩出しているところなら、自身にぴったりのペース配分や勉強法をレクチャーしてもらえます。
科目別の勉強法
財務会計論の勉強法
財務会計論は「計算」と「理論」の2つに大きく分けられ、計算は簿記の知識を求められる問題がほとんどです。簿記の仕分け・解法などを理解するには、とにかく何度も問題を解いて覚えていくアウトプットが重要。限られた時間で効率的に勉強するなら、同じトピックを2~3回繰り返す、1日以内に復習するなど、短時間で同じ問題を繰り返し解くことで記憶に残す学習法がおすすめです。
計算がアウトプット重視なのに対し、理論の財務諸表論はインプット重視の勉強法になります。テキストを繰り返し読み込み、問題集をひたすら解いていきましょう。定義や趣旨まで暗記する必要はないものの、合格圏内に入るには内容をしっかりと理解しておくことが重要です。短答については基本レベルをマスターできれば、それ以上時間をかける必要はありません。
管理会計論の勉強法
管理会計論は、公認会計士試験で財務会計論の次にボリュームの多い科目です。また、少し勉強した程度では正答が難しい問題も多いので、試験本番までに論点に関する徹底的な理解が求められます。原価計算では問題に応じて各種ボックスを書き分ける能力が必要となるため、何度も問題を解いて繰り返し書くことでボックス図の書き方を確実に習得しましょう。
手で書きながら覚える原価計算は時間はかかりますが、学習した内容を忘れにくいのがポイント。一方で管理会計は勉強にかける時間は比較的少なくて済むものの、個別論点が細かくなるので忘れやすいリスクがあります。そのため、学習初期は原価計算を優先し、管理会計は後から進めていくのが効率的な学習法です。
監査論の勉強法
監査論は公認会計士試験の短答科目のなかで最もボリュームが少なく、それでいて難易度の高い科目です。短答式では結論の正誤を求められるひっかけ問題が多いため、監査論を勉強する際は結論を暗記するための理解からまずは始めていきましょう。
テキストをざっくりと読んで全体像を把握し、問題を解いていきます。解法やテキストを確認して理解したうえで後日問題を解き直す、といったプロセスを自力で問題が解けるようになるまで繰り返すことが暗記につながるポイントです。
また、結論に至るまでの過程の理解が短答式・論文式のどちらにも求められるため、「どうしてこのような結果になるのか」を文字や図として書き出してみると自分の理解度も確認でき、記憶に残りやすくなります。
企業法の勉強法
企業法はそのほかの会計科目とは異なり、法律の知識が求められる科目です。企業法の短答式の効率的な勉強法としては「肢別チェックの繰り返し」と「市販の問題集の追加」の2つがあげられます。肢別チェックを繰り返し行なう理由としては、企業法の短答式は問題集をひたすら解いて確実にこなせるようにすることで80点以上も可能になるため。
覚える量が膨大な企業法はどれだけ多くの問題を解くかが重要になってくるため、勉強時間に余裕があれば市販の問題集も追加して頻出問題や出題傾向をつかみましょう。
論文式については、暗記力と答案作成スキルを磨くのが高得点を狙うためのポイントです。そのため、答案作成例の構成とキーワードをひたすら覚えていく勉強法が基本になります。効率よく覚える方法としては手帳を使った「思い出し作業」がおすすめ。勉強した内容を手帳にざっくりと書き込み、手帳を開くたびに読み返すことでよりインプットしやすくなります。
租税法の勉強法
公認会計士試験における租税法とは「法人税法」「所得税法」「消費税法」の3つ。特に法人税法は租税法の半数を占めるボリュームがあるため、法人税の総合問題対策は必須です。勉強法としては答練と復習を繰り返しながら、重要なポイントや頻出論点をインプットしましょう。特別賠償や圧縮記帳については難易度が高いわりに出題率が低いため、簡単な問題対策をしておく程度で問題ありません。
所得税法は、理論をマスターすることが第一。答練と復習を繰り返して知識をある程度身につけたら、法人税法の勉強を優先して、所得税法は知識が抜け落ちないように軽く復習するのがベター。また、計算については短期間でひたすら問題を繰り返し解き、記憶がまだ新しいうちに試験に臨むのがおすすめです。
消費税法の計算はほぼお決まりの出題パターンがあるので、問題集を使った反復学習が効率的な勉強法になります。ただ、租税法は問題数が多いため、出題パターンをつかんだらスピード感を磨いておくことも大切です。理論は計算を学んでいるうちに必要な知識が身についていくので、まずは計算をしっかりマスターして理論の勉強を進めていきましょう。
選択科目の勉強法
経営学
経営学は受験者の8割ほどが選択している科目です。基礎的な問題がほとんどであるため、ほかの科目よりも難易度が低いことが理由として挙げられます。主にファイナンス論と経営戦略論の二つを勉強する必要があります。ファイナンス論は計算式を暗記する数学寄りの勉強で、もう一方の経営戦略論は理論を暗記することが多く、単語をただ覚えていくという勉強内容です。
経営学は試験に合格したあとの業務にも活かせるため、特別な事情がないのであれば、経営学の選択をオススメします。
経済学
経済学は計算がメインとなり、微積分の知識も活用しなければなりません。出題範囲も広く、数学が得意でなければ解けない非常に難しい内容が出題される可能性があります。そのため数学が得意でない方は、避けた方が良い科目と言えるでしょう。もちろん経済学や数学が得意という方は、選択しても問題ありません。
数式などを覚え、解く必要があるため勉強時間は経営学よりも倍以上の時間を要するケースがほとんどです。そのため経済学を選択する受験生は少ないのが実情でしょう。
民法
民法は覚えなければならない条文も多く、適用範囲も広いため非常に長い学習時間を要してしまいます。ただ条文を暗記すれば良いというわけではなく、判例も踏まえて条文の内容を理解することが大切です。そのため選択する受験生は極端に少ないでしょう。法律を専攻しておりもともと得意分野である、という方や、民法が好きという方以外は避けた方が良いかもしれません。
統計学
統計学は、勉強する範囲自体はそう広くありません。暗記することも少なく、計算が得意な方にとっては選択しやすい科目と言えます。ただ計算内容は複雑であるため非常に高いレベルの知識・計算力が必要になるでしょう。しっかり解ければライバルに差を付けやすい科目ではありますが、一度計算ミスをしてしまえば取り返しがつかない可能性もあるので注意が必要です。その影響もあってか統計学を選択する受験生は少ない現状があります。
合格に近づく!押さえておきたい勉強法
公認会計士の試験に合格するためには、しっかりとした知識を身に着けることが大切です。ここでは押さえてほしい勉強法を紹介するので、ぜひ勉強する際の参考にしてください。
ただ暗記するだけでなく、知識として身に着ける
公認会計士の試験は幅広い出題範囲となるため、膨大な勉強をしなければなりません。もちろん試験の内容によっては暗記だけでも解ける問題もありますが、応用問題も多く出題されるので暗記しているだけでは解くことが難しいでしょう。そのため知識をしっかりと理解し、実際に使えるレベルにまで身に着けることが大切です。
覚えた知識を人に分かりやすく説明できれば、ただ暗記したのではなく身に着いているという証拠。一緒に勉強する仲間がいるのであれば、お互いに説明しあい正しい理解が出来ているかどうか確認するのも良い勉強方法です。この勉強法を繰り返し行うことで知識がより強固なものとなり、応用問題にも怯まずに挑戦できるでしょう。
苦手すぎる科目を作らないこと
公認会計士の試験は、1科目でも4割以下の点数を取ってしまうと不合格になってしまう恐れがあります。そのため極端な苦手科目をもつのではなく、各科目まんべんなく理解を深めておくことが大切です。
苦手な科目について、何をもって「苦手」としているのか改めて考えてみると、ほとんどの場合「基本的な知識を身に着けていない」ことが原因です。単に暗記しているだけで、本当の意味での理解はできていない可能性があります。じっくりと意味を考えながら勉強を進めていく方法が効果的です。次々に新しい知識を暗記するのではなく、時間をかけて理解度を深めるようにしましょう。
反復学習を行う
公認会計士の試験は、うろ覚えの知識で簡単に合格できるものではありません。試験で合格するためには、覚えた知識を即座にアウトプットできるかどうかが重要になってきます。このアウトプットができる状態まで知識を落とし込むためには、反復して学習することがポイント。
勉強法としては、知識を覚えて1回目は翌日に復習を行います。次の2回目は1週間程度、3回目は1ヶ月程度の間隔をあけるようにしてみましょう。できれば3回以上、徐々に間隔をあけながら反復して学習するのがオススメです。知識を何度も刷り込むことによって、簡単にアウトプットできる状態まで定着させることができるでしょう。
メリハリをつける
苦手科目に限らず、集中力を保ったまま長時間勉強を継続するのは難しいもの。集中力が欠けた状態で勉強を続けても、効率が落ちてしまいます。6時間以上ダラダラと勉強するよりも、集中して2時間程度勉強したほうが知識も身に着き、学習成果は得られやすくなります。集中する時間を設けることでオフの時間を確保できるので、心身のコンディションを整えやすくなるでしょう。
本場と同じ試験問題を実施する
公認会計士の試験をクリアするためには、実際の試験と同じように試験問題を繰り返し行い、徹底的に点数にこだわりましょう。点数にこだわることで今のレベルを明確にすることができ、何が足りないのか分析し、対応策を練ることができます。点数アップは、モチベーションにもダイレクトに影響する上、目標と現在地の距離を正しくつかめるなど様々なメリットが得られるはず。また試験問題に慣れておけば、本番にも強くなります。
強いメンタルが大切
どんな試験においても大切なのはメンタルです。「落ちるかも」「受かればいいな」程度の気持ちだと、試験に向けて学習のモチベーションを保つこと自体難しくなってしまいます。試験を受けるからには「絶対に受かる」という気持ちを持つようにしてください。この気持ちを保つことで、辛くなっても諦めることなく勉強を継続できるでしょう。
今すぐ見直そう!良くない勉強の仕方
必死に勉強しているはずなのに、なかなか結果に表れない。それは勉強の仕方が良くないのかもしれません。ここでは間違った勉強法について紹介していくので、自身の勉強法が間違っていないのか確認してみてください。
ただノートに書き写す
ノートに書くという行為はそれだけで勉強した気になってしまいがちです。しかし公認会計士の試験はノートに書き写すだけで合格するような内容ではありません。試験の範囲も広いため、すべてをノートにまとめることはできないでしょう。ノートをキレイに書くよりも、テキストを何度も読み込むようにしてみましょう。丁寧に一度書き写すより素早く何度も読む方が、多くの量をこなすことができます。
復習をしない
問題や試験問題を解いて満足していませんか?丸つけをして、点数だけ見て満足していませんか?
せっかく問題を解いたとしても、間違った箇所を見直していなければ意味がありません。どこが苦手なのかを分析し、理解できていない内容を何度も復習して学習することが大切です。しっかりと知識を身に着けるためにも、反復学習を行うようにしてください。
複数の教材を購入する
思うような成果が得られないからと言って、さまざまな教材を買い込んでいませんか?
複数の教材を使うよりも、一つの教材を何度も反復して行う方が、結果として得られる知識が増えます。まずは1冊をボロボロになるまで繰り返しましょう。
勉強時間を確保できない
公認会計士の試験は、半端な気持ちでは合格できません。プライベートな時間を勉強に割く必要もあるでしょう。長期的に学習しなければならないため、途中で誘惑に負けてしまう気持ちは誰しも理解できるもの。しかし、誰かがサボっている間も、公認会計士になるためにひたすら勉強している人は数多くいるのです。他の人たちに差をつけられないためにも、勉強時間をしっかり確保し継続するようにしましょう。
授業に出ることが目的
授業に出席し、講師の話を聞くだけで勉強した気分になっていませんか?
講師のレベルによって授業内容は大きく変わる上、ほとんどの場合は複数人の受講生のレベルに合わせて授業が進んでいきます。そのため自身のレベルに合っていない可能性もあり、場合によっては既に理解している内容を授業で聞くこともあるでしょう。授業に出るだけで満足するのではなく、本当に必要かつ為になる授業を受講するようにしてください。
まとめ
公認会計士試験の科目は、必須と選択を合わせて9科目。効率良く学習しなければ、試験までに間に合わない可能性も大いにあります。
今回紹介した勉強の順番は、あくまでもスムーズに勉強するための一例です。勉強の順番や各科目の勉強開始時期には個人差がありますので、プロの講師が在籍する通信講座などで聞いてみましょう。